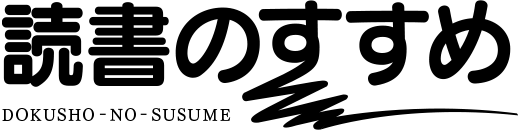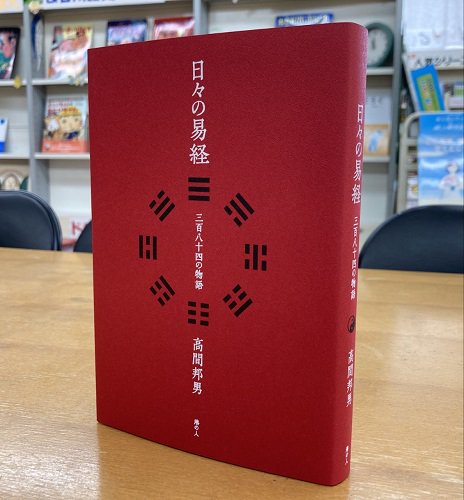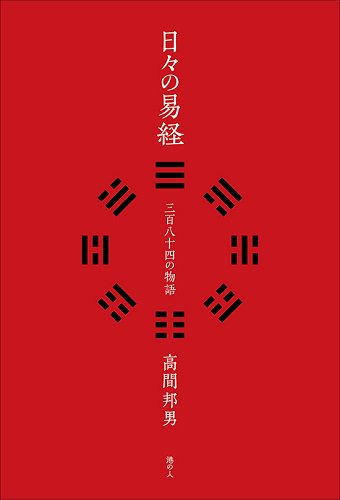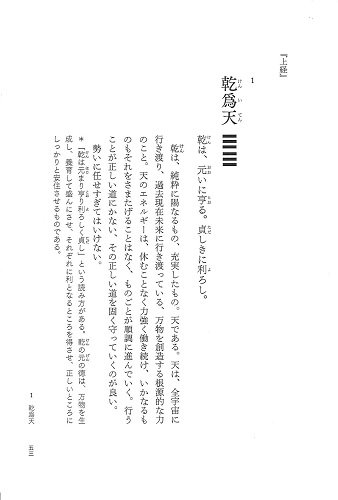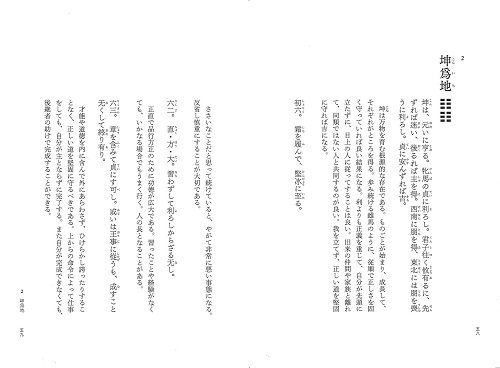�ڡְС�����������ΰ� ��ɴȬ���ͤ�ʪ��
2,530��(��230��)
���פ��֤�ΰ�����Τ����̾����
���ˮ����
����Ź�Ǥ�������������ܤ�����ŵ�ΡְСס�
���ޤ��͡��ʰФ�̾���ܤҲ𤵤��Ƥ��������ޤ�������
���פ��֤�ΰФ�̾���ǡ������⡢��̾���̤ꡢ�����˳褫����
�ְСפ������Ȥ��ƥԥå���Σ����Ǥ���
�äˡ���Ķ�� �С��ۡ���Ķ�� �Сٱ����ɤޤ줿���ʤɡ�
�ְСפ˶�̣���������ؤ�������Ȥ��Ƥ�������Ǥ���
�����⡢�����ܤϡ����Ҥγ��˶ᤤͳ�楬�ͤˤ��뾮���ʽ��ǼҤǡ�
����ǯ�ˤ錄��ְСפ椷�Ƥ������Ԥι�ֻ����ʸ�ʶ�����
�Ǥ�ʬ���䤹���褦�ˡ��Ż���ʹִط��ˤ�褫����褦�˹��פ���
����Ƥ���Τ����Ƥ�������ʤΤǤ��������ǼҤ���ळ�������
ɽ��μ꿨�����֡פο��礤�ʤɤ��碌�Ƥ��ڤ��ߤ���������
�ְФϺ�����3000ǯ�������μ��λ������Ω�������ۤǡ������λͽ�Ф�
��ŵ�ΤҤȤĤǤ��롣���ܤλ���ʸ���ˤ��礭�ʱƶ���Ϳ���Ƥ��ꡢ�Ť���������
��⳦�Υ���������ϰФ�ؤӡ��礭�ʷ��Ǥ�����פȤ��Ƴ��Ѥ��Ƥ�����
�פϡ������������ʪ�����Ѳ���64�Υѥ������ʬ�ष���Ѳ���ƻ�������餫�ˤ���
�ͤ��ɤΤ褦�˹�ư����ȡ�ʡ�������뤫���Ƥ��롣�ޤ�������ˤ��ޤ���
384��ʪ�줬�졢�����εȶ���ʡ��ؤ�������
�ܽ�ϡ�Ĺ����Ȥοͺ೫ȯ���ȿ���ȯ�˷Ȥ����ǡ�50ǯ�ˤ�錄�äưФ�
�����³���Ƥ������Ԥ���¿˻�ǡ���ʸ�ζ��ʸ���ͤˤ�狼��䤹���褦�ˡ�
�Ф��ҷä�ʬ����䤹�����⤷�����������
ϻ���ͷ��Ȼ�ɴȬ����β���ˤ�ꡢ�������ꤤ�εȶ���ʡ��ȤȤ�ˡ�
�����ΤǤ����Ȥ��Ф��ƤɤΤ褦�ʻ������٤��פ�٤�����ƻ��Ū�ʳؤӤ�
������褦�˽�Ƥ��ޤ�����
���ܽ�ϡ�˻�������ĸ�ʸ�ζ��ʸ���ͤǤ⡢�Ф��������������Ǵ�ñ�˳���
�Ǥ���褦�ˡ��ޤȤ�Ƥߤޤ������פ�ϻ���ͷ��β�������Ǥʤ���ɴȬ�����
���������ơ��������ꤤ�εȶ���ʡ������Ǥʤ��������Ǥ����Ȥ��Ф���
�ɤΤ褦�ʻ������٤��פ�٤�����ƻ��Ū�ʳؤӤ�������褦�˲��⤷�Ƥ��ޤ���
��ǯ�ˤ錄�äưפ����������פȤ��������Ƥ���ɮ�ԤȤ��ơ�����ä��餳������
�ܤ����ä�������뤷���פ˿Ƥ���Ǥ�����̼������������֤ˤ���Ǥ�館���
�ǤϤʤ����Ȥ��������ǡ��פ��ڤä����Ƥ�ѥ��Ȥˤ���������ѽ�Ǥ���
������
�ܽ��ϻ���ͷ��Τ��줾��η��η����ȸ������ʸ�Ȥ���ˤĤ��Ƥβ��⡢ϻ�
ૼ��Ȥ��β����Ǻܤ��Ƥ��ޤ����Фη�ʸ�ϡ���Ȥ�ȴ�ʸ����ʸ�ˤǤ��Τǡ�
�����ɤΤ褦�����ܸ�Ȥ����ɤ߲������ˤϡ��͡����ɤ���������ޤ���
�����ܤǤϡ���̾�ʽ��Ҥ��Ѥ����Ƥ����ɤ�������ӻ��Ȥ��Ĥġ�����ͤˤȤä�
��̣��ʬ����䤹���������ɤ���ɮ�Ԥ��פ��ɤ��������Ӥޤ������פϤ���ˤ��
�ֿʹ֤ϴ���䥨���Ȥ��ä���Ǻ�ȡ���������ĤΥХ��ȤäƷ��Ǥ���Τ�
����Ū�Ǥ������ۤȤ�ɤοͤϡ��ܤ����������ľ�̤����Ȥ��ˤϡ��ޤ��ǽ�ˡ�
�������ʬ�Ǥ��빥�������伫���ݿȡ��ߵƬ��⤿���Ƥ��ޤ������Ǥ���
������Ф���������������Ū��Ƚ�Ǥ��餯���Ф��Ҵ�Ū�˽����Ǥ�����ɤ��ΤǤ�����
�ʹ֤������Ϥ������ޤ���Ư��������ʬ�δ���Ū��Ƚ�Ǥ��������Ⱦ������뤿��ξڵ�
��Ϥ�Ƥ��ޤ������Ǥ���
���Ĥޤ꼫ʬ�ιͤ������������Ȥ�ʬ��Ǽ�������뤿���������Ư������褦�ˤʤ�
�������⤤�ΤǤ��������ʤ����бļԤ�������Ƚ�Ǥ��ܤ��ޤ餻�Ƥ��ޤ��ޤ���
���Ω�Ŀͤˤϼ����伫�椬�����ͤ�¿���Τǡ��ͤ�����Ƚ�����Ȥޤ��ޤ�ʹ������
�����ʤ��ʤ꤬���Ǥ�������ϡ��⤤���Ӥ�ơ����Ϥ���ͥ����ǧ����Ƥ���ͤ�
�٤�䤹��櫤Ǥ�������Ф����ɤ�����ˡ��������龼�¤�������⳦�Υ����
������¿���ϰФ�ؤ�Ǥ��ޤ�������ʬ���ꤤ��Ԥ������褬������ȯŸ���Ѳ�����Τ���
�����ơ�������Ф��뼫ʬ�ιͤ������ư�Τ��������䤦�ơ���ʬ���Ȥ��軰�Ԥ��ܤ�
ȿ�ʤ�����ʬ�λפ������ư�δְ㤤���Ф꤬�����ʤ��褦�˽������Ƥ����ΤǤ�����
����������η��Ǥ�����פȤ��ƤΰСפ��
<�ܼ����>
�Ϥ����
����
�����η��Ǥ�����פȤ��Ƥΰ�
�פ�����Ω��
�ڽ����
�Фλ��Ϳ�
�Фη����
���ۤȤ�
Ȭ���ΰ�̣
�̤ȱ�����Ȥ�
�ꤤ��(ά�ˡ)
�䤤��Ω�Ƥ�
ά�ˡ�μ��
��������Ȥä��ꤦ
�ꤤ�η�̤��ɤ�
�פεȶ�
�פ������
��
�ؾ�С�
�ز��С�
���ˮ����
����Ź�Ǥ�������������ܤ�����ŵ�ΡְСס�
���ޤ��͡��ʰФ�̾���ܤҲ𤵤��Ƥ��������ޤ�������
���פ��֤�ΰФ�̾���ǡ������⡢��̾���̤ꡢ�����˳褫����
�ְСפ������Ȥ��ƥԥå���Σ����Ǥ���
�äˡ���Ķ�� �С��ۡ���Ķ�� �Сٱ����ɤޤ줿���ʤɡ�
�ְСפ˶�̣���������ؤ�������Ȥ��Ƥ�������Ǥ���
�����⡢�����ܤϡ����Ҥγ��˶ᤤͳ�楬�ͤˤ��뾮���ʽ��ǼҤǡ�
����ǯ�ˤ錄��ְСפ椷�Ƥ������Ԥι�ֻ����ʸ�ʶ�����
�Ǥ�ʬ���䤹���褦�ˡ��Ż���ʹִط��ˤ�褫����褦�˹��פ���
����Ƥ���Τ����Ƥ�������ʤΤǤ��������ǼҤ���ळ�������
ɽ��μ꿨�����֡פο��礤�ʤɤ��碌�Ƥ��ڤ��ߤ���������
�ְФϺ�����3000ǯ�������μ��λ������Ω�������ۤǡ������λͽ�Ф�
��ŵ�ΤҤȤĤǤ��롣���ܤλ���ʸ���ˤ��礭�ʱƶ���Ϳ���Ƥ��ꡢ�Ť���������
��⳦�Υ���������ϰФ�ؤӡ��礭�ʷ��Ǥ�����פȤ��Ƴ��Ѥ��Ƥ�����
�פϡ������������ʪ�����Ѳ���64�Υѥ������ʬ�ष���Ѳ���ƻ�������餫�ˤ���
�ͤ��ɤΤ褦�˹�ư����ȡ�ʡ�������뤫���Ƥ��롣�ޤ�������ˤ��ޤ���
384��ʪ�줬�졢�����εȶ���ʡ��ؤ�������
�ܽ�ϡ�Ĺ����Ȥοͺ೫ȯ���ȿ���ȯ�˷Ȥ����ǡ�50ǯ�ˤ�錄�äưФ�
�����³���Ƥ������Ԥ���¿˻�ǡ���ʸ�ζ��ʸ���ͤˤ�狼��䤹���褦�ˡ�
�Ф��ҷä�ʬ����䤹�����⤷�����������
ϻ���ͷ��Ȼ�ɴȬ����β���ˤ�ꡢ�������ꤤ�εȶ���ʡ��ȤȤ�ˡ�
�����ΤǤ����Ȥ��Ф��ƤɤΤ褦�ʻ������٤��פ�٤�����ƻ��Ū�ʳؤӤ�
������褦�˽�Ƥ��ޤ�����
���ܽ�ϡ�˻�������ĸ�ʸ�ζ��ʸ���ͤǤ⡢�Ф��������������Ǵ�ñ�˳���
�Ǥ���褦�ˡ��ޤȤ�Ƥߤޤ������פ�ϻ���ͷ��β�������Ǥʤ���ɴȬ�����
���������ơ��������ꤤ�εȶ���ʡ������Ǥʤ��������Ǥ����Ȥ��Ф���
�ɤΤ褦�ʻ������٤��פ�٤�����ƻ��Ū�ʳؤӤ�������褦�˲��⤷�Ƥ��ޤ���
��ǯ�ˤ錄�äưפ����������פȤ��������Ƥ���ɮ�ԤȤ��ơ�����ä��餳������
�ܤ����ä�������뤷���פ˿Ƥ���Ǥ�����̼������������֤ˤ���Ǥ�館���
�ǤϤʤ����Ȥ��������ǡ��פ��ڤä����Ƥ�ѥ��Ȥˤ���������ѽ�Ǥ���
������
�ܽ��ϻ���ͷ��Τ��줾��η��η����ȸ������ʸ�Ȥ���ˤĤ��Ƥβ��⡢ϻ�
ૼ��Ȥ��β����Ǻܤ��Ƥ��ޤ����Фη�ʸ�ϡ���Ȥ�ȴ�ʸ����ʸ�ˤǤ��Τǡ�
�����ɤΤ褦�����ܸ�Ȥ����ɤ߲������ˤϡ��͡����ɤ���������ޤ���
�����ܤǤϡ���̾�ʽ��Ҥ��Ѥ����Ƥ����ɤ�������ӻ��Ȥ��Ĥġ�����ͤˤȤä�
��̣��ʬ����䤹���������ɤ���ɮ�Ԥ��פ��ɤ��������Ӥޤ������פϤ���ˤ��
�ֿʹ֤ϴ���䥨���Ȥ��ä���Ǻ�ȡ���������ĤΥХ��ȤäƷ��Ǥ���Τ�
����Ū�Ǥ������ۤȤ�ɤοͤϡ��ܤ����������ľ�̤����Ȥ��ˤϡ��ޤ��ǽ�ˡ�
�������ʬ�Ǥ��빥�������伫���ݿȡ��ߵƬ��⤿���Ƥ��ޤ������Ǥ���
������Ф���������������Ū��Ƚ�Ǥ��餯���Ф��Ҵ�Ū�˽����Ǥ�����ɤ��ΤǤ�����
�ʹ֤������Ϥ������ޤ���Ư��������ʬ�δ���Ū��Ƚ�Ǥ��������Ⱦ������뤿��ξڵ�
��Ϥ�Ƥ��ޤ������Ǥ���
���Ĥޤ꼫ʬ�ιͤ������������Ȥ�ʬ��Ǽ�������뤿���������Ư������褦�ˤʤ�
�������⤤�ΤǤ��������ʤ����бļԤ�������Ƚ�Ǥ��ܤ��ޤ餻�Ƥ��ޤ��ޤ���
���Ω�Ŀͤˤϼ����伫�椬�����ͤ�¿���Τǡ��ͤ�����Ƚ�����Ȥޤ��ޤ�ʹ������
�����ʤ��ʤ꤬���Ǥ�������ϡ��⤤���Ӥ�ơ����Ϥ���ͥ����ǧ����Ƥ���ͤ�
�٤�䤹��櫤Ǥ�������Ф����ɤ�����ˡ��������龼�¤�������⳦�Υ����
������¿���ϰФ�ؤ�Ǥ��ޤ�������ʬ���ꤤ��Ԥ������褬������ȯŸ���Ѳ�����Τ���
�����ơ�������Ф��뼫ʬ�ιͤ������ư�Τ��������䤦�ơ���ʬ���Ȥ��軰�Ԥ��ܤ�
ȿ�ʤ�����ʬ�λפ������ư�δְ㤤���Ф꤬�����ʤ��褦�˽������Ƥ����ΤǤ�����
����������η��Ǥ�����פȤ��ƤΰСפ��
<�ܼ����>
�Ϥ����
����
�����η��Ǥ�����פȤ��Ƥΰ�
�פ�����Ω��
�ڽ����
�Фλ��Ϳ�
�Фη����
���ۤȤ�
Ȭ���ΰ�̣
�̤ȱ�����Ȥ�
�ꤤ��(ά�ˡ)
�䤤��Ω�Ƥ�
ά�ˡ�μ��
��������Ȥä��ꤦ
�ꤤ�η�̤��ɤ�
�פεȶ�
�פ������
��
�ؾ�С�
�ز��С�